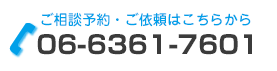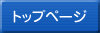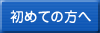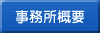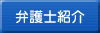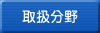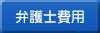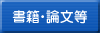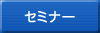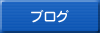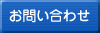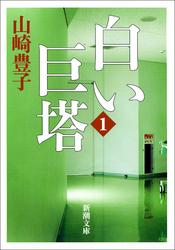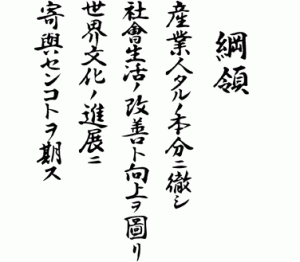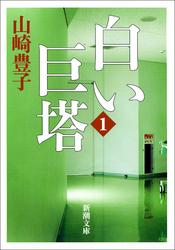 先日,作家の山﨑豊子さんが亡くなられました。
先日,作家の山﨑豊子さんが亡くなられました。
私は,「白い巨塔」の大ファンで,小説(新潮社)だけでなく,ドラマのDVDも旧シリーズ,新シリーズいずれも揃えています。
旧シリーズの財前五郎役の田宮二郎さんや,清潔感あふれる原告代理人弁護士役の児玉清さん(アタック25の司会をされていた俳優さん)は,いずれもはまり役で格好良かったですね。
さて,「白い巨塔」の大きなテーマの1つが,医療過誤裁判です。
私は,訟務検事時代に,大学病院や国立病院の医療過誤訴訟を担当していました。「白い巨塔」で描かれている大学病院の様子は,閉鎖的で,教授の権力が絶大であり,裁判に勝つためには証拠の偽造や偽証も厭わないというものです。
私が実際に経験したときは,時代が相当異なるので,さすがにそんなにひどいことはありませんでしたが。
ただ,医療過誤事件の打合せをするときに,教授,助教授(当時は准教授ではなく,この呼び名でした。),講師,助手といった方々が勢揃いしますが,教授の意見には口出ししにくいような独特の雰囲気があったことは事実です。
また,訟務検事のときには,国立病院で,脳の血管バイパス手術を見学する機会もありました。顕微鏡を用いた非常に繊細な手術で,執刀医の技術は超人的な神業に見えたものです。
医療過誤を担当すると,まずは,その分野で医学生が読むような標準的なテキストで基本的知識をつけ,関連する論文に目を通し,カルテを分析し,また,医師からも何度も話を聞いて,医学の専門的なことを理解しなければなりません。これは,相当骨が折れます。
また,論文の収集は医師にお願いすることが多いですが,医師側に有利な記述があると指摘された論文の別の部分に,裁判で不利になるような記述がなされていることもあり,きちんと全体に目を通さなければなりません。
医師は専門的知識が豊富にあるすぎるからか,文章を書いてもらっても,そのままでは裁判官に伝わりにくく,裁判の主張に使えないことも多くあります。これを,裁判所に分かるように,いわば翻訳することも,代理人の重要な仕事です。
医師による医療過誤が,時々,刑事事件となって立件されることがあります。その中で,裁判で過失の有無が争われ,時には無罪となる事例もあります。医療行為,特に手術は,もともと病気であったり,怪我をしている人の体を侵襲しますので,必ず一定のリスクが伴います。そのリスクについて,日々進歩し続ける当時の医療水準に照らして,許されるものであったかそうでなかったかを判断することは,非常に難しいことといえるでしょう。
弁護士は,医療の専門家ではありません。ただ,私の経験では,特定の事件で必要となる限られた範囲での医療の知識については,努力すれば,身につけることが可能だと思います。また,法律に照らして過失の有無を判断し,それを裁判官にどうアピールするかを選択することは,正に法律家である弁護士の得意とする作業です。
訟務検事のときに,難しい医療過誤事件を担当したことは,自分の知らない分野を勉強する方法論を身につけたという意味でも,自分にとって財産になっています。
刑事弁護の戦略の中で,一番,重要なことを挙げよと言われたら,それは何でしょうか。
私は,「ストーリーの発見」だと思います。
「ストーリーとしての競争戦略」(楠木建著・東洋経済新報社)という本がベスト・セラーになっていますが,成功する企業の経営戦略はストーリーがしっかり組み立てられていると言います。
刑事弁護もこれと同じで,しっかりとしたストーリーが組み立てられているのかどうか,がポイントです。
これには,警察や検察といった捜査機関による捜査の組み立て方が参考になります。
まず,誰かからの被害申告をうけるなどの捜査のきっかけがあります。
それに続いて,詳しい事情聴取,現場の見分,科学鑑定,関係者の事情聴取などの捜査を進めていきますが,その課程で,「この事件のストーリーはこうではなかろうか。」という仮説を立てます。
そして,証拠と合わせて,その仮説を適宜修正し,またその仮説に基づいて,「他にこんな証拠があるはずだ。」「こういう点を聞かなければいけない。」と考えて捜査の範囲を広げ,深めていき,最終的に,事件の詳細なストーリーを見極めます。
ですから,事件が摘発されるときには,既に捜査機関側のストーリーが組み立てられてしまっています。
弁護人としては,捜査機関のストーリーや証拠を単に批判するだけでは,受け身になってしまい,押し切られてしまいます。
将棋でも,「矢倉や穴熊で玉をしっかりと固めてから攻めよう。」とか,「相手から攻められる前に,速攻しよう。」といった構想力を持って指さずに,ただ,相手の手に対応しているだけでは,あっさりと負けてしまいます(参照:「構想力」谷川浩司著・角川書店,「上達するヒント」羽生善治・浅川書房)。
弁護人も,しっかりとした構想力をもって,事件のストーリーを構築しなければなりません。また,そのストーリーは,事件そのもののストーリーだけでなく,なぜ捜査機関が誤ったストーリーを組み立ててしまったのか,その原因について分析したストーリーも必要です。
そして,ストーリーを構築する方法は,大きく2つあります。
①依頼者から何度もしっかりと話を聞くこと
事件のことを最も知っているのは体験した依頼者です。捜査機関も,弁護人も,神様ではありませんから,真相を知っている訳ではありません。
謙虚にまず耳を傾けることが大事です。そうはいっても,依頼者本人が,何が重要で何が重要でないかが分からないために大事なことを言っていなかったり,あるいは自分に不利だと思いこんで,弁護人にも隠してしまうことがあります。
しかし,何が重要か,それが本当に不利なだけなのか,聞いてみて検討しないと分かりません。
依頼者から事件のストーリーを見極めるために必要な話を聞くには,時間とテクニックが重要です。
②想像力を働かせること
話を聞いた上で,もしそうであれば,他にこんなこともあるはずだなどと想像力を働かせる必要があります。
時には現場に行って距離感や周辺の様子をよく調べることも大事です。
こうではなかったか,あるいはこうか,などと何度も頭の中で事件を想像します。
カナダの作家のL・M・モンゴメリも,人間にとって一番大事なことは想像力だという趣旨のことを,その作品の中で主人公に言わせています(「赤毛のアン」村岡花子訳・新潮社)。
私も同感です。
何度もシミュレーションして,捜査機関に負けない,裁判所をより説得できるストーリーを構築すること。それが,刑事弁護の戦略で最も重要なことなのです。
企業には,さまざまな経営理念があります。
下に引用している写真は,時代を感じさせますが,パナソニックの理念です。
私も,独立するに当たって,当事務所の理念をどうするか,かなり時間をかけて考えました。松下幸之助の自伝を読んで,その「水道哲学」(水道をひねれば,安価に水が出てくるように,電化製品を社会の隅々にまで行き渡らせる。)には,感動しました。また,ビジネス書のロングセラー「ヴィジョナリーカンパニー」にも,「理念がしっかりしている企業こそが,成長する。」と指摘されています。私は,事業を営むに当たって,理念の確立こそが正に重要だと考えました。
弁護士の使命は,弁護士法によれば「社会正義の実現と人権擁護」とされています。また,個々の法律事務所によっては,「紛争の解決」や,もっと端的に依頼者のために「勝つこと。」「有利な結論を導くこと。」を理念としている場合もあります。
私は,社会正義や人権というのは究極の目標だとは思いますが,抽象的すぎてピンと来ませんし,正義といっても多面的であって,具体的な行動の指針にならないような気がしました。また,目の前の紛争を解決さえすれば,それで本当に足りるのだろうかとも思いました。
考えて見ると,好き好んで弁護士を訪ねて来られる方はほとんどおられません。多くは,トラブルに巻き込まれて,仕方なく,本当はこんなところに来たくないんだけど,やむを得ず来ておられます。そういう意味では,病院によく似ています。
そのようなトラブルに巻き込まれて悩んでいる方が,一番何を望まれているか。
私は,やはり,「安心」して,元の憂いのない生活に戻ることではないかと思います。紛争の解決自体や,面倒なことを弁護士に頼むことは,すべてそのための手段にすぎません。平穏な日常を取り戻して安心できる生活を将来も継続していく,そのためにこそ弁護士は依頼者の力になるべきだと思います。
そこで,私は,当事務所の経営理念は,「依頼者に安心を」以外にはあり得ないと思いました。
また,理念は単なるお題目ではなく,行動の指針となるべきものです。
そこで,私は,事件の方針の決定や具体的な処理に迷ったとき,どうすることが,長期的視野に立って,依頼者の安心につながるのか,ということを軸にして決めるようにしています。
依頼者への説明の仕方や,事務局スタッフの対応など,すべて「依頼者を安心させるためには,こういう話し方にしよう。こういう態度をとるべきだ。」という考えで統一するように努めています。
そして,私の専門の3つ,刑事,行政・税務,反社会的勢力対応に関係する依頼者は,日常生活や企業活動の中でも,最も重大なピンチに立たされており,不安のまっただ中におられます。そういう時にこそ,専門的な知識・経験を駆使して,依頼者に寄り添い,「安心」を与えること,それが,自分が弁護士であることの意味であり,使命だと思っています。
このように自分のスタンスが固まったことで,どんなに忙しくとも,困難な事件があろうとも,あまりストレスを感じずにすむようになりました。また,判断にもブレがなくなったような気がします。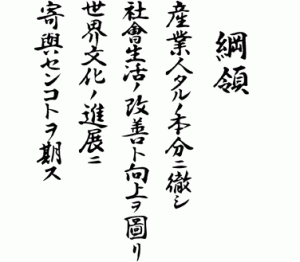
理念が固まれば,次は戦略です。事務所の経営戦略だけでなく,刑事弁護の戦略ということもずっと考えてきたことですので,続きは,戦略の話をしていきたいと思っています。
表題の「コモディティ化」とは,「汎商品化」ともいい,商品の個性がないことを指します。たとえば,自動車のように性能やデザインが問題となる商品と違って,ティッシュペーパーなどは一般的にはあまり商品の個性は問題にならず(厳密には,一部高級品などもありますが),どれもほぼ同じであって,消費者は安い商品を選ぶことになります。
法律事務でいえば,債務整理や過払い請求の事案では,全国展開している法律事務所や司法書士事務所があり,そのようなところでは,多数のスタッフによりマニュアル化された処理がなされているようです。いわば法律事務がコモディティ化しているといえます。
これと同様に,刑事弁護をマニュアル化し,実際に担当する弁護士個人の経験年数にかかわらず,それぞれの事件で類型ごとに同じような処理を行うことは可能でしょうか。
そもそも債務整理や過払い請求についてマニュアル化して,弁護士が実際に依頼者に面談することもなく,スタッフ中心に形式的に大量処理をすること自体にも,私は疑問があります。
目の前の事件を法律に従って形式的に処理することだけが目的ではなく,紛争を解決し,依頼者に最適なアドバイスをすることで,長期的に依頼者に安心を与えることが弁護士の仕事だと思うからです。
債務整理をしなければならない依頼者には,何か原因があるはずです。収入よりも支出が恒常的に多くなっているので,借金が増大しているわけですから,なぜそうなっているのか丁寧に聞き取って,今後,同様の事態が発生しないようにはどうすれば良いか,具体的なアドバイスも求められるはずです。
また,弁護士がきちんと会って面談して,話をすることは,依頼者にとっての重みが全く違うと思います。それが短時間であったとしてもです。いくら,債務整理の事務処理そのものがマニュアル化可能だからといって,大切なことを軽視して,ただ,大量処理することが弁護士のサービス向上になるとは思えません。
しかし,弁護士による個人の債務整理は,実際には,コモディティ化してしまい,初回相談無料,着手金無料などのサービスによる価格競争となっています。
それでは刑事弁護はどうでしょう。
確かに事件の類型,逮捕,勾留といった手続段階でとるべき手段などについて,ある程度,マニュアル化は可能でしょう。
しかし,私は,検事時代を含めると,これまで数千件の刑事事件の捜査や裁判に携わりましたが,どんな事件にも,それぞれ特有の個性があります。
接見に行って,黙秘権があることや供述調書は署名する前によく確認すること,署名する義務はないことは常にアドバイスしますが,それだけでなく,どのように取り調べに応じればいいのかについて具体的なアドバイスは,事件の内容,依頼者の個性などによって違います。また,不服申立ての手段を取るのか,取るとしてどのタイミングでどの手段をとるのか,検察官や警察官と面談して交渉するとして何をどう伝えるのか,意見書は出すのか,出すとしてその内容は,被害者がいるとして示談の交渉をどのようなタイミングでどう行うかなど,その組合わせは複雑であり,とても単純にマニュアル化できるものではありません。
また,捜査中には,弁護人は捜査の記録を見ることはできませんから,経験に基づく推測を前提に活動をしなければいけないという点もあります。
私は,刑事弁護という活動は,弁護士の職務の中でも,非常に高度で難しいものであると感じており,今でも,悩みながら慎重に行っています。
いわば刑事弁護は,経験と研鑽に基づく職人的な仕事であって,マニュアル的な大量処理には最も向かないサービスです。だからこそ,プロとしてはやり甲斐があるという面があるのだと思います。
ですから,刑事弁護はコモディティ化できない,経験のある弁護士が専門的に取り扱うべき分野であるというのが私の答えです。
 競馬により多額の払戻金を得た方に対して,儲けを大きく上回る所得税の課税がなされ,単純無申告罪として刑事責任を問われた件の続報です。
競馬により多額の払戻金を得た方に対して,儲けを大きく上回る所得税の課税がなされ,単純無申告罪として刑事責任を問われた件の続報です。
報道のとおり,今年の5月23日に,有罪判決にはなったものの,はずれ馬券の購入費も全額経費に認められるという実質納税者勝訴といっていい判決が出ました。
その後,検察官が控訴し,現在,大阪高等裁判所に事件が係属中です。検察官からの控訴趣意書がいまだ提出されていないため,期日も決まっておりません。
また,刑事事件とは別に,課税処分の取消しを求めて,大阪地方裁判所に行政訴訟も提起しておりますが,これも,国側と主張のやりとりをしている段階で,まだ結審はしていません。
いずれも,国側が何か月もの準備期間を取っており,「時間稼ぎ?」と思われる面がないではありません。
ひょっとしたら,国税庁内部で競馬の課税についての制度を議論していて,それに時間を要しているのかもしれませんが,よくわかりません。
調べたところでは,アメリカ合衆国では,競馬の配当金については,はずれ馬券も配当金で得た金額を上限に全額経費として認められているようです。
日本では,きちんとした制度設計をしないままでした。そして,従来の素朴な考え方に基づいて課税をしたため,今回の事件のような不合理な処分となっています。
マスコミの取材で何度もお話しましたが,私は,競馬の払戻金については非課税の立法措置を施して欲しいと思っています。それが結局,競馬の売上を上昇させて,国庫の収入増加をもたらすのではないでしょうか。
これ以上,依頼者を不安定な状態におかないように,また高額馬券の配当を受けた人を不安に陥れないように,はやく解決して欲しいと心から望んでいます。
弁護士の中村和洋です。
ブログを始めることにいたしましたので,よろしくお願いいたします。
このブログでは,私の最も関心のある
1 刑事弁護のこと
2 行政事件や税務事件のこと
3 反社会的勢力対応のこと
について,主に書き連ねる予定です。
私の専門というべき分野は,上記の3つですが,これはいずれも,トラブルの中でも,当事者にとって最もストレスのきつい,大変にしんどいことです。
刑事事件や行政・税務事件は,相手が国家権力など強大である点
反社会的勢力対応は,相手が犯罪的な組織であったり,常識の通用し難い暴力的な人間である点
において,個人や一企業が向かっていくには,相当の気構えが必要です。
こういう一番ややこしいトラブルに巻き込まれてしまったらそれに対処するしかないのですが,防止できるなら防止するに越したことはないと,私は,この仕事を続けていく中で,つくづく思うようになりました。
そこで,最近は,紛争予防の観点から,中小企業のコンプライアンス指導や,労務問題,事業承継問題へのアドバイスに力を入れています。
そういった,大きなリスクを防止するための,中小企業の経営サポート的な話もしていければと思っています。
どうぞ,よろしくお願いします。